第九話 碧海の彼方(5)
飛び出しそうに打ち鳴っている心臓を胸に抱えながらも、アンドレスは、もう一つ深く息を吸い込むと、意を決した横顔を毅然と上げた。
そして、ビルカパサが開いた天幕の垂れ布をくぐり、天幕の内部へと踏み込んでいく。
広大な天幕の内部は、眩い幾つもの燭台の灯りに照らし出されており、その光にアンドレスは、一瞬、目を瞬かせた。
そして、再び瞼を開けると、相変わらず興奮と緊張に震える瞳を凝らす。
次第にはっきりとしていく彼の視界の中で、トゥパク・アマルは、多くの護衛兵に囲まれた天幕中央の椅子に座し、真正面からこちらを見ていた。
燭台の光を目元に反射させる研ぎ澄まされた切れ長の目、濡れたように輝く絹のような漆黒の長髪、そして、黒マントをゆるやかに纏ったガッシリと引き締まった長身――それは、かつてアンドレスが共にありし日と変わらぬトゥパク・アマルの姿であった。
(トゥパク・アマル様……!!)
あまりの感動なのか、安堵なのか、張っていた「気」が一気に抜けたためなのか、ともかく、アンドレスは足から力が抜けて、殆どその場にへたり込みそうになった。
だが、トゥパク・アマルがゆっくりと手招きする指先に吸い込まれるように、アンドレスは、天幕の奥まで歩み進んでいく。
今、ほんの数メートルを隔てた距離に至っても、まだ、どこか放心したように立ち尽くしているアンドレスを、トゥパク・アマルの漆黒の瞳が、静かながらも厳然たる力を宿して見つめている。
「アンドレス――…」

深遠な、あまりに懐かしいトゥパク・アマルの声音に、アンドレスはハッと目覚めたように勢いよく地に跪いた。
そして、深く身を屈めて恭順の礼を払う。
「トゥパク・アマル様!!
ただ今、ラ・プラタ副王領より戻りました!!」
トゥパク・アマルは、ゆっくりと頷いた。
「よく戻った、アンドレス」
そして、あの低く響く声で、平伏しているアンドレスの背に向かって言う。
「顔を上げよ」
トゥパク・アマルの声に促されるままに、アンドレスは、すっかり紅潮した顔を上げる。
直近で見上げるトゥパク・アマルの美しくも精悍な輪郭に宿る、以前と変わらぬ沈着な面差しに、アンドレスは、今、本当に生身のトゥパク・アマルと対面していることを実感して、言葉に尽くせぬ深い感動を噛み締めた。
恍惚とした大きな瞳を揺らしながら、感極まった眼差しで己に見入っているアンドレスの様子に、トゥパク・アマルも、目の色を和らげる。
そして、その口元にゆるやかな微笑を浮かべた。
「アンドレス、そなたは変わっていないようだな」
「トゥパク・アマル様も!!」
嬉々として応えるアンドレスに、トゥパク・アマルは、思わず苦笑する。
「そうか――わたしも変わっていないかね?」

他方、アンドレスは、再び、渾身の力を込めて決然と頷いた。
「はい!!」
そして、跪いたまま、ぐっと身を乗り出して、ますます激しく揺れる瞳でトゥパク・アマルを凝視する。
次の瞬間、そのアンドレスの肩がわななくように震えたかと思いきや、大きく見開かれた彼の目から、どっと涙が溢れ出した。
さすがにトゥパク・アマルも息を詰める。
それから、燭台の光を映す目元を、静かに細めた。
「アンドレス、わたしの捕縛の件では、そなたにも、ずいぶん心配をかけたことあであろう。
すまなかった」
一方、アンドレスは、とどまるところなく溢れ出した涙を、片手で懸命に押さえ込みながら、ひたすら首を振っている。
そして、顔を上げられぬままではあったが、跪いた姿勢で背筋を真っ直ぐ伸ばして身を正すと、涙声ながらも決然と言う。
「俺は…また、こうしてトゥパク・アマル様の元で戦えると信じていました――!!」
トゥパク・アマルも、ゆっくりと、そして、力強く頷いた。
「わたしもだ。
アンドレス――」

トゥパク・アマルの言葉に、周囲の兵たちの存在も忘れて、いよいよアンドレスは天幕の地に大粒の涙を落としながら、嗚咽を漏らして動けなくなっている。
そのような彼を、トゥパク・アマルは静寂な面差しで見守っていた。
やがて、必死で己を落ち着けると、アンドレスは充血した目を何とか上げた。
そして、真剣な表情になって、トゥパク・アマルを見据える。
「トゥパク・アマル様に、ご報告しておかねばならぬことが……!」
「何だね?
申してみよ」
「実は…アリスメンディ殿のことなのです。
アリスメンディ殿は、我が軍に同行して、当陣営まで来ております」
「!――」
さすがのトゥパク・アマルも、その切れ長の目を見開いた。
「何故、アリスメンディ殿が、そなたの軍に同行してきたのだ?」
トゥパク・アマルの不意に険しくなった声音に、アンドレスは反射的に身を固めた。
「アリスメンディ殿は、インカ軍に力を貸したいと、それで、トゥパク・アマル様のいらっしゃるこの本営まで同行したいと希望されて――」
「その言葉を、そのまま信じたのか?」
「はい……!」

いつしかトゥパク・アマルは、褐色のしなやかな指先を額に添えたまま、その目元をやや吊り上げて、アンドレスをじっと見下ろしている。
他方、トゥパク・アマルの様子に、アンドレスは思わず視線を落として固唾を呑み、地に添えた指先を握り締めた。
「アンドレス、彼が英国側の密偵であったら、とは考えなかったのかね?」
「…――」
アンドレスは、ぐっと唇を噛み締める。
そして、激しく打ち鳴る鼓動をおさめようと懸命に深く息を吸い込むと、意を決した眼で、きっぱりとトゥパク・アマルを見上げた。
「俺は、アリスメンディ殿は、信じられると思いました…!!」
そう言い放ったアンドレスを見下ろしたまま、トゥパク・アマルは鋭利な目元を聳(そび)やかす。
「何故、そう言い切れる?」
「――勘です……!!」
「勘…?」
「アリスメンディ殿の中には、我々と同じものが――!!」
「我々と同じもの――…」
トゥパク・アマルは、鋭くも厳格な面差しで、暫し、貫くようにアンドレスを見据えた。
「なるほど。
そなたが、そこまで、はっきりと信じられると感じたのであれば、そなたの感じた通りなのかもしれぬ。
わたしとて、そうであってほしいと願っている」
「トゥパク・アマル様……!」
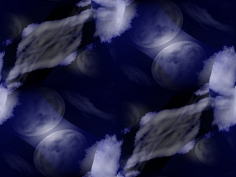
アンドレスが何か言いかけたのを、トゥパク・アマルのしなやかな指先が、サッと鋭く宙を切って遮った。
「確かに、わたしはアリスメンディ殿と連絡を図った。
そして、それによって、アリスメンディ殿は英国艦隊を動かした。
だが――互いの利害や思惑が一致しているかどうかは、また別の問題だ。
双方、それを分かった上で、動いているのだ。
分かるかね?
今の状況は、いろいろと複雑だ。
一つ駒の動かし方を過(あやま)てば、致命的なことにもなりかねぬ」
「――……!!」
「アンドレス――わたしも、そなたも、己の判断と選択に、過大なリスクを伴っていることを、よく自覚しておろうな?
つまりは、その結果に対する責の重さは、そなたの命をもって償っても足らぬほどのものであるということも。
それは、わたし自身にとっても言えることではあるが――」
険しく、厳然としつつも、一語一語を噛み含めるように語るトゥパク・アマルの言葉を聴きながら、アンドレスの横顔を、つっと、冷たい脂汗が伝って流れた。

一方、いつしか相手の方に前傾姿勢になっていたトゥパク・アマルは、己の顔にかかっていた前髪を鋭い手つきでかきあげる。
そして、低く、早口で――しかし、決して冷ややかではない声音で――言った。
「アンドレス、そなたは、もう下ってよい。
そなたも、そなたの兵たちも、今のうちに、しかと長旅の疲れを取っておきなさい」
他方、アンドレスは、まだ喉元に何かたくさん突っかかったままのような居たたまれぬ感覚を覚えていたが、今は、到底、それ以上を言える空気ではなかった。
ぎこちなく礼を払って彼が姿を消すと、トゥパク・アマルは思慮深くも鋭利な横顔のまま、傍に控える家臣に告げる。
「英国側の斥候たちが、既にその辺りをうろついているかもしれぬ。
作業現場の周辺を特に厳重に監視せよ。
アリスメンディ殿にもだが、決して、敵方の目に触れさせてはならぬ。
――それから、今宵、早速にも、アリスメンディ殿と二人で話したい。
わたしの元へ呼んでくれたまえ」
その頃、当のアリスメンディは、本営の一角にて、インカ兵たちの手助けを受けながら、住まう天幕の準備を行なっていた。
その中にはロレンソも混ざっており、天幕を張るインカ兵たちに指示を送りながらも、その目は、常にアリスメンディの一挙一動に注がれている。

やがて、野営の準備が整い兵たちが立ち去ると、アリスメンディは天幕の一隅に腰を下ろして荷をほどきながら、少し離れた位置で火鉢の火をくべているロレンソに視線を向けた。
「ロレンソ殿、そう始終わたしに付き添っているのも大変であろう?」
「いえ」と、ロレンソは常の鋭利で沈着な表情のまま、感情を交えず応える。
「わたしは、あなた様の護衛官を申し付かっております。
お傍に付き従うのは、当然のことです」
他方、アリスメンディは、その面差しに揺れる蝋燭の影を映しながら、ふっと苦笑する。
「わたしは、それほどに怪しいかね?」
「怪しいなどと…――!」
ロレンソは、感情的になりかけた声音をすぐに押さえた。
そして、何事も無かったように、再び火鉢の火を煽りながら淡々と応える。
「アリスメンディ様、わたしは、あなた様がインカ軍にいる間は、あなた様をお守りする義務がある。
それだけです」
その時、天幕の入り口に、先刻までとは別の筋骨逞しいインカ兵が現れた。
その手には、煌々と燃え上がる松明が握られている。
「何用か?」
ロレンソの問いに、兵は俊敏に礼を払うと、天幕の奥にいる黒衣の僧へも素早く礼を払った。
「アリスメンディ様にご伝言です。
皇帝陛下が、あなた様とお会いしたいとのことでございます。
お迎えに上がりました」
「トゥパク・アマル様が…!!」
息を詰めるロレンソの向こうでは、アリスメンディが、刃のごとく鋭利に研ぎ澄まされた面差しに、不敵とさえ見える笑みを浮かべている。
「ほぅ…こうも早々に、トゥパク・アマル殿がお目通りくださるとは。
ありがたき幸せに思います。
すぐに参りましょう」

ほどなくアリスメンディが通された天幕は、先ほどアンドレスが通された広大な広間のごとく天幕とは趣が異なり、やや小規模で、かなり奥まった場所だった。
とはいえ天幕の外周は、夜空に燃え上がる幾多の松明と厳(いかめ)しい衛兵たちにビッシリと取り囲まれている。
「アリスメンディ様、お待ちしておりました!」
天幕の前で待ち構えていたビルカパサが、その厳(いか)つい褐色の身を沈めて、黒衣の僧に深く礼を払った。
礼を払いながらも、その敏捷な目線はアリスメンディの全身をくまなく一巡し、僧が武器の一切を身に付けていないことを素早く視認する。
そして、敬意を込めた手つきで天幕の垂れ布を開いた。
「さあ、どうぞ中へお入りください。
陛下がお待ちでございます」
天幕の中に踏み込むと、ものものしい外周とは別世界のような、静寂で、落ち着いた空間が待っていた。
陣営内とは思えぬ格調高い調度品が並べられ、燭台の数もほどよく調整されて、適度な暗さに保たれている。
そこは、天幕の中というよりも、むしろ西洋風邸宅内の客間か書斎のごとくであった。
内側から入り口の垂れ布をしっかりと下ろし、アリスメンディは、ゆっくりと内部に進み行く。

探るように鋭利な彼の視線の先に、鏡のように磨き抜かれた艶やかな長テーブルが見え、そして、その前に座しているトゥパク・アマルの姿が目に入った。
燭台の炎が光沢を帯びた長髪を闇に浮き上がらせ、美麗な面差しと相まって、その気配は妖艶でさえある。
武器も持たず、傍に護衛の一人もつけずに、ただ静寂なたたずまいで、単身、そこにいるトゥパク・アマルの姿に、アリスメンディは鋭い目を細めた。
そんなアリスメンディの姿を認めると、トゥパク・アマルは椅子を立って、真っ直ぐこちらに歩みくる。
褐色の肌に漆黒の長髪、そして、黒ビロードの長マントを肩から巻きつけたトゥパク・アマルの姿は、裾長の黒衣で全身を覆った己自身よりも、さらに深い闇を纏ったかのような格好であった。
だが、冷徹、且つ、沈着であるはずのアリスメンディの目にさえ、トゥパク・アマルの黒で統一された強靭な長身を、蒼く透明な覇光が包みながら静かに渦巻いているのが見える。

アリスメンディは鋭利な目で、さらに近づいてくる相手を貫くように見据えた。
そしてまた、トゥパク・アマルも、その研ぎ澄まされた切れ長の目で、黒衣の僧を鋭く見つめた。
が、すぐに視線を伏せるようにして、深く丁寧に礼を払う。
「アリスメンディ殿、お久しぶりでございます」
アリスメンディも、険しくなりかけた目元を、素早くゆるめた。
そして、胸で十字を切って、礼を払う。
「トゥパク・アマル殿――本当に。
かれこれ、12〜3年ぶりであろうか」
「さあ、こちらへ」と、トゥパク・アマルに促されるままに、アリスメンディは重厚な造りの長テーブルに据えられた椅子へと着座した。
他方、僧と90度の位置に座ると、トゥパク・アマルは、しなやかな手つきで、つっと、グラスを相手の前に差し出した。
そして、滑らかに光るワインボトルを傾け、静かに微笑む。
「いかがですか?」
アリスメンディも鋭利な目を僅かに伏せて礼を払うと、グラスを傾けた。
天幕周辺には、あれほど多数の衛兵がひしめいているはずなのに、内部は驚くほど静かだった。
トゥパク・アマルが、優美な手つきでワインを注ぐ音のみが、心地よく耳に響いてくる。
熟成された果実の芳香が、微かに立ちのぼった。
アリスメンディの手にあるグラスを満たす赤い液体は、やや離れた位置にある燭台の光を反射して、宝石のように美しい煌きを放っている。

その液体をゆっくり喉に流し込むと、アリスメンディはグラスを置きながら、ふっと吐息を漏らした。
「昔から、この地のワインは、実に味が良い。
またこうして味わえる日が来ようとは…――」
真に感慨深気に語るアリスメンディの横顔を見つめながら、トゥパク・アマルも切れ長の目を細めて、微笑する。
そして、誠意を込めた深遠な声音で、改めて、深く礼を払った。
「アリスメンディ殿、わたしの書状をお読みくださり、迅速に英国王室を動かしてくださったこと、心よりお礼申し上げます」
「いや、トゥパク・アマル殿――」
アリスメンディは、ゆっくりと首を横に振る。
「礼を言うのは、わたしの方だ。
トゥパク・アマル殿のおかげで、この国を追われたわたしが、こうして、再び、この南米の大地を踏みしめることができたのだから」
「アリスメンディ殿……」
互いの面差しを見つめるそれぞれの瞳の奥に、静かに、激しく、燃える燭台の炎が映っている。
相手の瞳を見つめたまま、トゥパク・アマルが、再び口を開いた。
「アリスメンディ殿もご存知のことと思うが、十数年前、あなた方、イエズス会の神父様方が去られてからは、この国では、暗雲がいっそう深く、重く、立ち込めて参りました」

トゥパク・アマルの言葉を受けて、アリスメンディの目元が、刃のように鋭い閃光を放つ。
「我らが追放された後の、この国のキリスト教会の動きは、英国にいたわたしの耳にも幾ばくかは届いております。
今では、あのモスコーソ司祭殿が、すっかり台頭しているようですな」
アリスメンディの言葉に、トゥパク・アマルは黙って頷く。
そして、感情を隠すかのように、己のグラスの方へと視線を伏せた。
その横顔をじっと見つめながら、アリスメンディは、今一度、グラスに唇を触れる。
それから、皮相な笑みを浮かべて、低く囁いた。
「その様子では、トゥパク・アマル殿も、あのモスコーソ殿に、大分、痛めつけられておりますな。
大方、『副王への反逆は、神への反逆に他ならぬ――!』などと、すっかりキリスト教への反逆者呼ばわりされていることでありましょう」
「――ふ……」
あまりにそのままのアリスメンディの言葉に、思わず、トゥパク・アマルも苦笑する。

夜の深まりと共に外では風が強まり、天幕の中にも隙間風が吹き込みはじめる。
このサンガララ周辺の山岳地は、アンデス一帯の中でも特に気温が低く、流れ込む夜風は強い冷気を帯びている。
暫し、二人は、風に煽られる蝋燭の火を見つめていたが、やがて、トゥパク・アマルが、真摯な光を宿した目を上げた。
そして、そのガッシリと強靭な肩を、真っ直ぐアリスメンディに向ける。
「アリスメンディ殿、あなたは、かつても我らインカの民のために、己の全てを投げ打ってくださった。
あの時、国外追放までされたあなたを、我らは、どのような打つ手も持てなかった。
にもかかわらず、此度のわたしの呼びかけに快く応じ、英国艦隊まで動かしてくださった。
そのような、あなたのために、わたしに何か報いることができるだろうか?
このような言い方をするのは、あなたに対して失礼かもしれぬが――敢えて、単刀直入に尋ねさせてほしい。
今、あなたは、何を望んでいる?
真のあなたの望みは何なのです?」
しかし、アリスメンディは鋭利で沈着な面差しを変えることなく、ただ、ゆっくりと首を振る。
「わたしは、神の御心が果たされることを願うのみ。
それ故、神は、わたしをあなた方、インカの民の元へと遣わされた。
それだけのこと。
わたしには、個人的な望みなど、元々、ありはしないのです」

「アリスメンディ殿」
トゥパク・アマルは、黒衣の僧の方へと瞼を伏せて、今一度、深く礼を払う。
「それでは、神は、我らインカの民の解放が成就することを真に望んでおられると?」
アリスメンディは、相手から鋭い視線をはずさぬまま、無言で頷いた。
「アリスメンディ殿、あなたの我々に対するお心は良く分かりました。
とはいえ、あなたは、形式上は、今も英国艦隊側の相談役というご身分を降りてはいないご様子」
「!――」
トゥパク・アマルの言葉に、アリスメンディは訝しげに目元を聳(そび)やかす。
「トゥパク・アマル殿…――何が言いたい?」
他方、トゥパク・アマルは沈着な佇まいを変えぬまま、閃光を放つグラスの向こうから続けていく。
「どうか誤解の無きように。
わたしは、あなたのお心までを、英国側の人間だなどとは思っておりません。
わたしの発言の失礼をお許しください。
ただ、あなたは、形の上では、まだ、英国側の人間であることは事実。
わたしと接触を図った以上、英国のために有益なお働きを為すことができねば、我らの元にお留まり頂くことも叶わなくなりましょう?」

ますます面差しの鋭くなっていく相手を前に、トゥパク・アマルは、ゆっくりと光るグラスを持ち上げ、唇に触れた。
「英国艦隊は、今や世界最強と言われる実力。
ですが、スペイン軍も決して弱小ではない。
ましてや、ここは英国艦が得意とする外洋ではなく、馴染みのない最果ての敵地。
それに対して、スペイン軍にとっては、己の庭のごとく懐の内――」
「そういえば……トゥパク・アマル殿。
すっかり申し遅れていたのだが――」
トゥパク・アマルの言わんとしていることを察してか、アリスメンディの口元から、思い出したかのように低い囁きが漏れる。
「此度の英国艦隊総指揮官ジョンストン提督より、あなた方のために、多数の武器を預かってきております」
「ほう、それはありがたい」
トゥパク・アマルの瞳が、静かな閃光を放つ。
「それで、その武器とは、いかほどですか?」
「銃剣類を中心に、ざっと1万5千点ほど。
今は、スペイン軍の目につかぬよう、沿岸部の一角に隠し置いている」
「そうでしたか」と、トゥパク・アマルは、その瞼を伏せて、アリスメンディの方へと深く礼を払った。
「それでは、その武器は、提督の率いる英国海軍のためにお役に立てねばなりますまい」
「――……」
トゥパク・アマルの言葉の意味を探ろうと、無言のまま、僧侶とは思えぬ鋭利すぎる目で刺すように見据えくる相手に、トゥパク・アマルは意味ありげに目を細めた。
そして、その美しい口元に微笑を浮かべる。
「単純なことです。
英国軍にとっても、我らにとっても、当座の敵はスペイン軍。
それに、あなたがたの持ち込んでくれた武器のことは別としても、敵を窮地に追い込むための策を、我らとて練っていないわけではない……」

含みをもたせて語りつつ、次第に見開かれゆくトゥパク・アマルの切れ長の目が、相手の鋭利な視線を貫いて光る。
「もちろん、そのためには、英国艦隊が攻撃を開始するタイミングを、我らも正確に把握しておく必要がありますが――」
それから暫くの時が流れ、アリスメンディが天幕の中から外へと姿を現した。
入り口の外で護衛をしていたビルカパサが礼を払うと、アリスメンディも無言で礼を払う。
表情を動かさぬ黒衣の僧からは、ビルカパサをはじめ、周囲の衛兵たちの誰もが、彼とトゥパク・アマルとの間で交わされた会話の内容を推察することは不可能だった。
天幕の外で控えていたロレンソが素早くアリスメンディの傍に参じ、僧の天幕へと導いていく。

他方、精悍な横顔で、その二人の後ろ姿を見送っていたビルカパサは、背後から不意に何かの気配を感じて、敏捷に振り返った。
そして、その目を瞬かせる。
「アンドレス様!?」
いつの間にか己の傍に立っていたアンドレスの姿に、ビルカパサは驚いて見入った。
「アンドレス様、いつからいらしたのです?!」
「すいません、驚かせて…!
今、来たところです。
何となく落ち着かなくて。
そろそろトゥパク・アマル様とアリスメンディ殿の話が終わる頃かと思って」
そう言いながら、アンドレスは所在無げに頭をかいている。
ビルカパサは低く息をつくと、誠実な瞳で頷いた。
「確かに、アンドレス様のお気を揉む気持ちは、分かります。
トゥパク・アマル様とお話をされていきますか?
アリスメンディ殿も戻られたところですし、お取次ぎを……」
そう言って天幕の中に入りかけたビルカパサを、「いえ…!そこまでは…!」と、アンドレスの手が、慌てて相手の腕を掴み、引き止めた。
が、その瞬間、二人の前で、天幕の入り口が、すっ、と内部から開け放たれた。
「――!」
ギックリとして見上げるアンドレスを、案の定、中から姿を現したトゥパク・アマルが黙って見下ろしている。
「すいません…!!
トゥパク・アマル様、あのっ……」
すっかりドギマギして言葉に詰まっているアンドレスに、トゥパク・アマルは、ゆっくりと移動して内部への通り道を開け、静かに言った。
「アリスメンディ殿のことが気になるのであろう。
入りなさい」
再び天幕の中に戻ると、先刻までアリスメンディが座していたのと反対側の位置にアンドレスを座らせ、トゥパク・アマルは新たなグラスを取り出して相手の前に置いた。
一方、アンドレスはすっかり緊張の面持ちで、そのグラスに赤い液体が注がれていくのを、戸惑いながら見つめている。
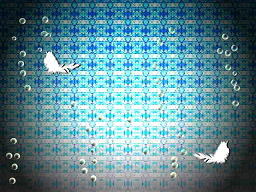
見るからにカチンコチンになっているアンドレスの方に、トゥパク・アマルは己のグラスをゆるやかに掲げた。
「そう硬くなることはない。
さあ、アンドレス、そなたとそなたの軍の帰還を祝して」
「え…?!
あっ、ありがとうございます…!!」
思いがけぬトゥパク・アマルの言葉に急に昂(たか)ぶったのと、もともとの緊張とで、アンドレスは反射的にグラスを手に取り、一気にそれを飲み干した。
そして、放心したようにグラスを置き、深く息をつく。
「フゥーッ…――」
青くなったり赤くなったりしながら、すっかり舞い上がっている様子のアンドレスに、トゥパク・アマルは微苦笑を湛えながら、己のグラスを口元に運んだ。
やがて、アンドレスは、意を決した面持ちで、トゥパク・アマルの方へと向き直った。
「あの、トゥパク・アマル様…!
アリスメンディ殿とお話をされて、どうだったでしょうか?」
「どう、とは?」
「その…つまり……」
アンドレスは居住まいを正し、拳を膝で握り締めながら、ぐっと身を乗り出した。
「アリスメンディ殿は、密偵でしょうか?!」

真剣に問うてくるアンドレスを見つめながら、トゥパク・アマルは、ゆっくりとグラスを下ろす。
瞬間、微かな硝子音が、静寂な空気を振わせた。
「それは、わたしにも分からぬ」
「トゥパク・アマル様……」
再び訪れた沈黙の中で、燭台の炎が隙間風に煽られ、揺れている。
その不安定な光を見つめながら、トゥパク・アマルは、低く続けていく。
「だが、その意図はどうあれ、アリスメンディ殿が今も英国側と連絡を図っているのは確かであろう」
「――…!!」
返す言葉に詰まるアンドレスの前で、トゥパク・アマルは、やや目を伏せて思慮深い面差しになったまま、今はそれ以上を言う気配はなかった。
アンドレスは、ますます落ち着かぬ心境で、どうにも所在無く、周囲の空間に視線を泳がせる。
この天幕の中は、本当に、まるでどこかの屋敷の書斎か居間のように見える。
目の前にある重厚な長テーブルの少し先には、精緻な彫刻を施された書棚まで据えられており、そこには書物や書類の束が整然と並べ置かれている。

アンドレスは強張った心境ながらも、つい興味を惹きつけられて視線を動かしていく。
そして、ふと、棚の一隅で燭台の光を受けながら、煌く白光を放って見える何物かに目がとまった。
(あれは…?!)
思わず目を凝らしているアンドレスの様子に気付いて、トゥパク・アマルも、その視線の先を追う。
「ああ、あれは模型だ」
「え?
模型?!」
トゥパク・アマルは黙って頷くと立ち上がり、棚からその何物かを両手に掲げ持ってきて、アンドレスの目の前に置いた。
「これは……!」
それは非常に精巧に組み立てられた、見事な帆船模型であった。
重厚さがありながらも隙の無いスマートな船体、凛然と聳(そび)える高く頑強な3本のマスト、そして、全マストには純白の帆が華やかな翼のように広がっている。
その艶やかな白い帆布に燭台の炎が反射して、帆船全体が白光に包まれているかのように見えるのだった。

さらに、帆船後部にある艦尾側面には、精緻な彫刻で飾られた窓々があり、蝋燭の灯りを受けて燦然と煌いている。
その眩さにうっとりと見蕩れているアンドレスの視線の先を、トゥパク・アマルも見やった。
「その艦尾部分には、提督や艦長の個室がある。
それ故、実際の艦(ふね)も、とても豪奢に造られている」
「艦長たちは、帆船の前の方ではなくて、後ろ側にいるのですか?」
アンドレスの素朴な問いに、トゥパク・アマルは、艦尾にある、前方甲板部分よりも一層高くなった後甲板を指し示した。
「艦の舵は、普通、艦の後方にあるものだ。
それ故、艦長たちも、この艦尾部分で指揮を執る」
「指揮……」
そう呟きながらも帆船のあまりの優美さに心を奪われたように見入っているアンドレスの耳に、再びトゥパク・アマルの声が低く響いてくる。
「そう。
戦の指揮を執る者がいる艦。
いかに美しい帆船であろうとも、これは、恐るべき殺傷力を満載した軍艦だ」
「こんな綺麗な船が…軍艦…――!」
トゥパク・アマルのしなやかな指先が、すっと、艦の側面を滑るように指し示していく。
その指先のなぞる場所には、船体の側面から黒々と突き出した無数の大砲が連なっていた。
しかも、その黒光りする砲列は、ズラリと横並び一列のみではなく、それと同様の砲列が、船底に近い部分から甲板に近い上部まで、三層に渡って船体左右側面に並んでいる。
一体、全体で何台の艦砲が据えられているのか、到底、数え切れぬほどである。

アンドレスは、にわかに蒼ざめて、微かに震える唇を噛んだ。
「こんな凄まじい砲撃力を備えた艦が、軍団でこの国に向かってるってことですか……?!」
「そうだ。
しかも、当地に到着するまで、もう、そう遠くはない」
トゥパク・アマルのいつにも増して低く凄みの宿った声音に、アンドレスは、己の背筋に、ジワリと冷たいものが滲み出すのを感じた。
現実と知りつつも、まだどこか絵空事のようにも思えていた英国艦隊の襲来――その事実が、急に強度の真実味を帯びて迫りくる。
いくらトゥパク・アマルが意図的に呼び寄せたものとはいえ、これほど威力のあるものを、どうにかできるというのだろうか?!
(一体、どうなってしまうんだ…これから……!!)
トゥパク・アマルの前では決して言葉に出せずとも、アンドレスは、そう叫び出したい衝動に駆られずにはいられなかった。
それを懸命に堪える彼の強張った喉元が、引きつりながら固唾を呑み込む。
そして、その傍では、トゥパク・アマルもまた、非常に険しい面差しで、恐るべき凶器を秘めた美麗な艦を見つめていた。
ところで、その頃、インカ帝国旧都クスコでも、新たな胎動が起こっていた。
クスコ市街地の一角にある高級酒場――かつて、トゥパク・アマルが脱獄を図るために、番兵リノを遣わした、あの酒場である。
元々はインカ族の富裕層の人々が利用し、且つまた、その裏側では、表立って反乱には加わっていずともトゥパク・アマルの息のかかった富豪たちが、密かに溜り場としていた場所でもあった。

そして、最近では、植民地生まれの白人たちも、この酒場に出入りしては、水面下の会合を重ねていた。
スペインの植民地になってからも、この国から搾り取った莫大な利益を享受していたのは、本国スペイン生まれの上層部に属する、ごく一部の人々のみにすぎない。
それ故、同じスペイン人でありながら、この植民地で生まれたというだけで蔑まれ、貧しい生活を強いられ、激しく抑圧されてきた当地生まれの白人たちもまた、重大な不平分子であったのだ。
トゥパク・アマルはそれを良く知っていたからこそ、その反乱の大義として、インカ族や黒人たちの解放のみならず、混血児や、彼ら南米生まれの白人たちの解放をも高らかに掲げていた。
しかしながら、モスコーソ司祭のトゥパク・アマルに対する過酷な弾圧を目の当たりにするにつれ、敬虔なカトリック教徒である白人たちは、司祭の容赦無い仕打ちを恐れ、表立って反乱に協力することには消極的になっていた。
だが、彼らの中にくすぶっていた革命への火種が、消えていたわけではない。
この酒場に集まっていた白人たちも、また、そうした不平分子たちであった。
口の堅い、それでいて、どこか彼らに懐柔的なインカ族のマスターに見守られながら、夜ごと、多数の男たちが入れ替わり立ち現れては、安煙草の紫煙の中で夜を明かす。
ある者たちは過酷な現実に暗く溜息をつき、また、ある者たちは革命への理想を熱く語りながら。
そして、今、そのような彼らの中心に居て、男たちの話を仕切り、自らも情熱的に革命への思いを語っている人物がいた。
それは、まだ20歳代半ばと見える若者だった。
高級酒場の重厚な雰囲気とは場違いなほどに、貧しい装いの植民地生まれの白人たち――だが、その若者だけは、スペイン貴族の肖像画から抜け出てきたかのように、格段に身なりが良い。
だが、その高貴な装いとは裏腹に、その風貌は精悍で精気に溢れ、野性的でさえある。

そして、今、集ったそれら当地生まれの白人たちの間でも、専らの話題は、やはり目前に迫った英国艦隊襲来のことであった。
痩せ細り、色褪せて擦り切れたシャツを着込んだ男たちだが、しかし、彼らの眼光は、その骨ばった輪郭の中で、不気味に炯々と輝いている。
もはや、天災であろうが、人災であろうが、この国の体制が大混乱に陥るならば、いかなることであろうが歓迎だ、と言わぬばかりの目の色である。
中心にいる若者は煙草をくゆらせながら、興奮ぎみに語り合っている周囲の男たちを悠然と見渡している。
その貫禄ある態度は、到底、20代半ばそこそこの若者には見えない。
そんな彼に、周りにいる数名の男たちが、物欲しそうな視線を投げかけた。
若者は、黙って懐から精緻な銀細工の施された煙草入れを取り出し、男たちの方へと差し出した。
たちまち、方々から無数の手が伸び、競い合うように、真新しい煙草が挿し抜かれる。
瞬時に空になった煙草入れを懐に収めると、若者は、厚い胸板をそらし、深く煙を吸い込みながら低く言う。
「おおかた、英国艦隊を呼び寄せたのは、あのトゥパク・アマルだろう」
にわかに、周囲が、どよめいた。
「だけど、シモン殿、トゥパク・アマルは獄中に囚われているはずではないのか?」
シモンと呼ばれたその若者は、短くなった煙草を、トッと、灰皿に打ちつけながら、ゆっくりと首を振る。
「未だ処刑の告示の気配も無ければ、随分前から牢獄周辺の警備も手薄だ。
トゥパク・アマルが囚われた当初、スペイン軍が意気揚々と組んだ広場の処刑台など、今では、すっかり朽ち果てている」
「なんと、わざわざ、見に行ったのか?
処刑台まで…!」
驚き呆れたような周囲の声に、シモンは、その均整の取れた男性的な横顔に苦笑を浮かべた。
「まあな。
把握しておかねばならんことだ」

「だが、トゥパク・アマルが脱獄しているならば、何故、あの者は姿を現わさない?
インカ族の者たちでさえ、囚われていると思い込んで、今も泣き暮らしているというのに
…!」
「むろん、それは、英国艦隊襲来のタイミングを図ってのことだろう。
だから、英国艦隊の到来が迫った今、遠からず、あの男は民衆の前に姿を現す」
そう言いながら、若者は、琥珀色に光るピスコのグラスを傾けた。
アルコール度数42度をくだらぬ強い酒の芳香が、その手元から立ちのぼる。
「英国艦隊の襲来、そして、トゥパク・アマルの再来で、もうすぐ、この国はひっくり返ったようになるだろう。
さて、諸君、そろそろ、我らも身の振り方を決めねばなるまい」
だが、周囲はざわめきながら、にわかに腰を引く。
「シモン殿、それは、トゥパク・アマルに加担するかどうかということか?」
「しかし、我々はスペイン本国からの独立は望んでも、インカ帝国の復活なぞは願ってはおらん」
「もちろんだ」
シモンは手元の酒を一気にあおると、荒々しくグラスを置いた。
そして、強い眼光の閃く目で、周囲の一人一人を見渡していく。
「いまさら、帝政や君主制なぞ…!
だが、これほどの好機を見過ごすなど、愚かなことだ。
植民地支配体制の瓦解――まずは、それが実現しなければ、何も始まらん」


